「私は少し変わっているのかもしれない」――そう感じたことはないだろうか。
こんな経験
- 人との会話がどこかちぐはぐになる
- 集中力の波が激しく、物事を忘れやすい
- 完璧主義で、失敗を強く恐れる
こんな経験をすると、ふと「自分は普通じゃないのかもしれない」と不安になる瞬間がある。
どんな人でも、おかしいところなんてどこにもないのだ。
これは、介護福祉士やメンタルケア心理士を学んでいる私ではなく、1人の人間として伝えたい言葉だ。
たとえ診断を受けたとしても、1人のかけがえのない人間だという、あなたの本質は変わらない。
自己理解は、個性として受け入れるところから始まるニャ。
私自身も、長いあいだ「生きづらさの正体」を探してきた。
専門家ではないけれど、自分の内面を言葉にすることで、少しずつ光が見えてきた。
この記事では、その体験と心理学の知見をもとに「自分を肯定する」自己理解のプロセスをまとめている。
✅この記事の概要
- 私自身の生きづらさを、心理学の視点から整理。
- 生まれつきの特性を「個性」として受け入れる方法を紹介
- 筆者自身の赤面傾向・完璧主義・ネガティブな特性を再構築
- カウンセリングや自己理解の学びを通じて、「苦しみと共に生きる力」を育む
- 自己理解とは、自分を言葉にし、ありのままを受け入れること
🪞この記事は「自己理解シリーズ」の第2弾。前後どちらから読んでも理解できる構成になっている。
自己理解シリーズ第1弾
ビッグファイブ診断と人生史で紐解く「本当の自分」
今の自分の性格は、どのように作られてきたのだろうか。 遺伝、環境、そして他者との関わり。様々な要素が複雑に絡み合っていることは疑いようがない。 自分の過去を闇…
目次
人は、みんな違う
ここで紹介する枠組みが「生きづらさ」を感じている原因を決定づけるものではありません。
メンタルケア心理士®1を学ぶ中で得た知見を元に、私の自己理解に必要な事前知識として紹介しています。
また、他者に対して「○○症かもしれない」といった言及をすることは医学的な診断行為にあたる可能性があり、決して行うべきではありません
なお、ここで述べる内容はすべて私自身の内省と自己診断によるもので、医療的な判断や診断ではありません。
生まれつきの特性という枠組み
人には、生まれつき脳の働き方に特徴や偏りがある。
こうした「生まれつきの特性」が、日常生活の中で影響を及ぼすことがある。
ただし、これは「脳の異常」ではなく「働き方の違い」にすぎない。
たとえば「集中力が続かない」「注意がそれやすい」という傾向があっても、日常生活にまったく支障がない人もいる。
注意力の差や感覚の敏感さ、対人コミュニケーションの難しさなど、現れ方は人それぞれ。
こうした違いは「欠点」ではなく、脳の多様性(ニューロダイバーシティ)として理解されている。
パーソナリティという視点
人には、生まれ持った性格の傾向がある。
パーソナリティ(性格)の形成は、遺伝的な要因と環境的な要因の2つが複雑に影響し合って形づくられる。
この「遺伝と環境」という2つのピースは、社会という文脈の中で、「不安やストレス」に影響を及ぼすこともある。
こうした傾向は「パーソナリティの多様性」であり、「病気ではなく心のクセ」として捉えられる。
たとえば、慎重さが強く現れる人もいれば、完璧を求めすぎて自分を追い込んでしまう人もいる。
どちらも「間違っている」わけではなく、性格の一部が少し極端に表れているだけだ。
たとえば、非行を繰り返す人がいたとしよう。
「親の育て方が悪い」「性格に問題がある」と考えてしまう人もいるかもしれない。
しかし、反社会性も人が生きる上で身につける「防衛のかたち」のひとつだ。
人は誰しも、傷つかないための自分なりの防衛を持っている。
それがときに「反発」や「拒絶」として表に出ることがあるだけだ。
やはり、おかしな人なんて誰もいない。
客観的に「変わっている人」に見えても、一貫した核(コア)となるパーソナリティは、確かに存在している。
私の人生史
詳しい人生史は以下に記載している。ここでは箇条書きで簡潔に自己紹介をまとめてみよう。
簡単に言えば「いじめと人間関係での失敗、社会での失敗を繰り返している人生」だ。
運営者の自己紹介(箇条書き)2025/10
- ごく普通の家庭で育つ。感受性が強く、泣き虫で人の目を気にしやすい子ども。
- いじめを経験し、不登校に。物語の世界に救われる。
- 家庭内で1度だけ、暴力を受ける
- 中学・高校の学力は低く、自己肯定感が下がっていた。
- 高校卒業後に専門学校へ進学するが、勉強に挫折して中退。
- 恋人ができるが「重い」と言われ破綻。強い自己否定に陥る。
- 無職時代にスマホゲームやSNSに依存し、現実からの逃避が続く。
- アルバイト工場勤務を経て介護職へ転職
- 読書、哲学、自己理解、自己啓発、健康活動を深める
- 介護資格を取得し、誠実に働く一方で赤面症を発症。共感疲労と人間不信を抱える。
また、手先が不器用で運動音痴、学力が低く、その上で完璧主義だ。
私の個性を再構築する
ではここからは、私自身の個性を、実際にポジティブに再構築してみよう。
赤面傾向と社交不安の気づき
私は現在、赤面しやすい傾向を持っている。
集団での会話や、自分の内面を語る場面になると「赤面するかも」と分かる瞬間があり、言葉がうまく出てこない。
これは、次のような要因が関係していると思われる。
- 生まれつきの気質
- いじめやトラウマ、失敗の積み重ね
- 人間関係をなるべく避けてきた影響
以前は、それを「弱点」だと思っていた。
しかし、今では自分の感受性の高さがもたらす自然な反応のひとつだと理解している。
こうした特性は社会の中で生きづらさを感じる要因にもなる。
それと同時に、不安からくる感受性の高さは、観察力・誠実さ・他者への思いやりを育ててもくれた。
赤面するというのは、心が誠実に反応している証拠だ。
「恥ずかしい」ではなく「心を守ろうとしている」からこそ起こるサインでもある。
今では、赤面も自分の大切な一部だと感じている。
赤面は、脳が「自分を守ろうとしている」サイン
全てを受け入れられているわけではないが、この気づき以来、赤面は恥ずかしいものではなくなった。
「誠実さと感受性を伝えるサイン」として、少しずつ前向きに受け入れられるようになってきた。
こだわりが強い傾向
私は性格の傾向として「強いこだわり」を持っている。
- コミュニケーションや対人関係の難しさ(集団では言葉が出てこない)
- 人間関係を維持するのが苦手(いわゆる関係リセット傾向)
- 興味が限定的(心理学はそこそこ、芸能や時事には疎い)
- 1度没頭すると何時間でも同じ作業を続けられる(読書・ブログ執筆など)
- 何事も、ルーティン化が前提(健康習慣としても機能している)
- 対人関係や環境の感覚刺激に敏感
これらはあくまで自己理解から得られた「少し苦労した経験」の範囲だ。
ただし、昔のように困ることはほとんどなくなった。
むしろ、これらの特性は今では自分の強みとして働いている。
特に「没頭しやすい」という特徴は、集中力や創造力として発揮
没頭できる趣味で日常を満たすことで、孤独感の解消している
対人関係でも「赤面するから何?」というくらい、自然体でいられる
困っていないからこそ、今はむしろ「将来の孤独リスク」という新たな課題に向き合っている。
人は社会的な生き物であり、孤独には本質的に弱い存在だからだ。
それでも、これらの傾向を受け入れ、活かしながら生きている自分を肯定できている。
残されたテーマは、「どう孤独と共に生きるか」という未来への問いだけだ。
学習に対する「変わった傾向」
私は昔から、文字や文章を書くことに苦労している。
特に「読む」「書く」そして、それに伴う文法や構成の整理が苦手という傾向がある。
- 手書きの際、文字を正確に書けず誤字が多くなる(博士が、博博になる)
- 履歴書など一発勝負の場面では、集中力と時間が必要で、それでも失敗することがある
- 授業中に「聞きながら書く」ことが難しく、板書を写すのが遅れる
- 文章を書くとき、段落構成や主語・述語の位置がずれてしまう
- 文章を読む際、場面を想像しないと意味が頭に入ってこない(かなりの遅読)
- 学んだ内容を言葉にまとめるのが難しく、意味のある文章に起こすのが苦手
まとめると、これは「文字や言葉を理解する〈脳の経路〉が他の人と少し違う」可能性がある。
- 一般的な認知スタイル
:文字 → 言語 → 意味
- 私の認知スタイル
:文字 → イメージ → 意味
- 一般的な処理経路
:学習 → 言語化 → 記憶
- 私の処理経路
:学習 → 感覚的・体験的理解 → 言語化
これを裏付けるように、外国語や古文、漢文など「言語変換が複雑な分野」は特に苦手意識が強い。
これらの特性は、学生時代の学力にも影響していたと思う。
当時は「怠けている」「勉強が嫌い」と誤解されやすく、自分でもうまく説明できなかった。
今ではスマホやパソコンの入力環境が助けになり、思考をより自由に言語化できるようになった。
かつての「苦手」は、デジタルツールとの相性の良さとして活かされている。
つまり私は〈文字〉や〈言葉〉を「イメージや体験」として理解するタイプ。
一般的な学び方とは違うだけで、理解の仕方が少し違うだけなのだ。
超が付くほど不器用で、運動音痴
私は、おそらく他者がびっくりするほど不器用で、運動音痴だ。
これは、練習量とかそのようなレベルではない。
- ボウリングで、10点以上取れない
- リフティングが、5回以上成功したことがない
- ゆっくりと投げられた物でも取れない(反応できない)
- 料理中に考えられない理由で大怪我(ショッキングなので伏せる)
- 階段を降りようとして転げ落ちる(別に急いではいない)
- 基本的に、身体の精密な動きが必要なことは難しい
これら一部の理由は、とある理由で頭部MRIを受けた時に判明した。
私は、人よりも小脳が小さい(あくまで個人差の範囲)
といっても生きる上で支障はまったくなく、ハンデというほどではない。(日常生活や人格形成にはほぼ影響しない)
これには昔から苦労してきたことではあるが、他者と比べて「できない」だけで、私になんの関係があるだろうか?
たしかに日常生活で気を付けることはあるが、それ以外は他者との比較でしかない。
この点は、私の人格には一切影響を与えることには値しない。
強迫的な思考パターン
私には、やや「強迫的な思考パターン」がある。
おそらく一部は、こだわりが強い傾向や、いじめ体験、過去の失敗経験が影響していると思う。
- さまざまな場面で完璧主義が強く出る(あきらかに過剰)
- 他者に仕事を任せにくい(自分の手順通りでないと落ち着かない)
- お金を使うことに抵抗がある(ただし本や学びに関しては例外)
- 効率よりも「手順通りであること」を重視する
- 本棚の並びを「高さ・分厚さ・タイトル・色」など複数の基準で分類したくなり、最終的に矛盾して諦める
完璧主義的な部分では困ることも多い。
極端なときには「絶対にこうしなければならない」という強い感情さえ生まれる。
また、お金に関しても「無駄を出したくない」という意識が強く、買い物や交際面では少し慎重すぎるかもしれない。
それでも、私はこの傾向を「健康習慣を徹底できる性質、内省を継続する性質」として活かしている。
さらに、ルーティン化が得意な特性と組み合わさることで、日々の生活や自己管理では大きな強みになっている。
私は「内向型」である
あなたは内向型?それとも外向型?
ここまで振り返ってみると、ふと考える。「私はどこかおかしいのだろうか?」
――いいや、違う。
私はただ、人と少し違うだけだ。
今の私は、自分の性質を「内向型」と受け止め、そのままの生き方を肯定し、幸福を見出している。
こだわりの強さは、1人の時間を深め
学習の変わった特性は、物語への没入力を育て
強迫的な思考パターンは、健康習慣の継続力につながっている。
これらはすべて、外から与えられたものではなく、内側から自然に湧き上がる衝動だ。
私は自分を「内向型」であり「内的刺激追求型HSP」だと考えている。詳しくは「ビッグファイブ×人生史」の記事へ
ただ、科学的な「外向性/内向性」でいえば、幼い頃に外で友達と走り回るのが好きだった。
私は、本来は外向的な気質を持っていたのかもしれない。
だからこそ今は、外向的なエネルギーを〈内的な探求〉へと向けて生きている。
それが、私にとっての「内向型としての幸福」のかたちだ。
〈内向型〉は、病気や異常ではなく、心の働き方や感じ方のひとつのあり方です。
私はその枠組みを、自分の特性をポジティブに理解しやすくするための言葉として用いています。
あわせて読みたい
内向型とは何か?外向型との違い
内向的な性格は、社会の中ではときに「デメリット」のように扱われてしまうことがある。 面接やプレゼンでうまく話せない 人と過ごすのも楽しいのに、一人の時間がどう…
1人で悩む必要はない
私は専門家ではないが、これらの自己理解を手助けするのか、カウンセリングというお仕事だ。
踏み出す勇気を持つ
もし今、あなたが「生きづらい」「自分だけおかしいのでは」と感じているだろうか?
まず知ってほしいのは――それはあなたのせいではないということだ。
人はみな、生まれも育ちも、脳の働き方も違う。
あなたが感じている苦しさは、ただ「少し違う仕組み」で世界を受け取っているだけなのかもしれない。
診断を受けることがゴールではない。
けれど、もし日常生活に支障を感じているなら、専門家に相談することは「弱さ」ではなく「自分を守る行動」だ。
カウンセリングや通院は、心を治すためではない。
あなたの特性を理解し、これからの生き方を整えるためのサポートだ。
勇気を出して一歩踏み出せば、あなたの〈生きづらさ〉は〈自分らしさ〉に変わるかもしれない。
苦しさを言葉にするのも勇気ニャ。一歩ずつで大丈夫ニャ。
自分を知る民間資格|こころ検定
通院やカウンセリングに行く勇気がないときは、まず「学び」から始めよう。
「なにを言っているんだ?」と思うかもしれないが、自分の心を客観的に知るための資格が本当に存在する。
それが「こころ検定」だ。
私自身も学んでいる「メンタルケア心理士®」資格では、この検定2級の合格が必須条件になっている。
実際にこの記事の内容の多く、およそ6割は「こころ検定2級テキスト」から得た知識を基にしている。
こころ検定のレベルは次のとおりで、自分の心の仕組みを理解したい人には4級・3級がおすすめだ。
- こころ検定 4級:こころの基礎を学ぶ(心理学の入門)
- こころ検定 3級:心理学の全体像を知る(ストレスや感情の理解)
- こころ検定 2級:実践的な心理支援の基礎(メンタルケア心理士®)
- こころ検定 1級:専門的なカウンセリング理論(メンタルケア心理専門士®)
一歩踏み出す勇気が出ないときでも、「学び」を通じて心を知ることは、確かな自己理解への第一歩になる。
こころ検定【文部科学省後援】公式サイト
カウンセラーは心の悲鳴を聞くお仕事
カウンセラーという仕事は、「話を聞く人」ではなく「言葉にならない心の声を聴く人」だ。
- 理由の分からない不安が続く
- 何もないのに涙が出る
- 過去の傷が今も心に残っている
人は誰しも、助けを求めながらも「大丈夫」と言ってしまう瞬間がある。
その沈黙の奥にある痛みや葛藤を、安心して出せる空間をつくること――それがカウンセラーの役割だ。
そして、そのためには知識よりもまず、共感と受容の姿勢が大切になる。
相手を変えるのではなく「苦しかったのですね」と寄り添う力だ。
私自身も、学びを通して「誰かの無言の悲鳴を聴ける人」でありたいと思うようになった。
ただ、私の性質上、人と深くコミュニケーションを取ることが難しい面もある。
だからこそ、このブログがある。内向型ラボは、私自身をカウンセリングする場所だ。
同じように生きづらさを抱える人の心を少しでも軽くしたいという願いから生まれた。
苦しみをなくすのではなく、苦しみを抱えながらも生きられる強さを支える。
それが、カウンセラーという仕事の本質だと私は思っている。
話を聞いてもらえるだけで、心が少し軽くなることもあるニャ。
結論|自己理解とは「自分を言葉にする」こと
苦しかった過去も、逃げ続けた過去も、すべてを受け入れて一つの物語として語る。
それが「ナラティブ・アプローチ」と呼ばれる、自分の人生を再構成する対話法だ。
本来はカウンセリングで使われる手法だが、静かに自分と向き合うことで、自分でも行うことができる。
自分を言葉にする――最初は、どうしてもネガティブな言葉が出てくるかもしれない。
けれど、それでいい。ネガティブな自分をも受け入れることこそ、自己理解の第一歩なのだ。
あなたは、ありのままの姿で、すでに美しい。
自分を好きになる
セルフコンパッション|「自分を責めない」ためにできること
「自分はなんてダメな人間だろう」―― そう感じたことが、一度はあるのではないだろうか。 何をやっても失敗してしまう 自分には取り柄なんてない 人より劣っている気が…
✨ この記事のまとめ
- 「生きづらさ」は欠点ではなく、心の働き方の違いから生まれる。
- 特性を否定せず、個性として理解することで、自分との関係が変わる。
- 苦しみをなくすのではなく、苦しみと共に生きる力を育てる。
- 自己理解とは、過去を受け入れ、自分を言葉にしていくプロセス。
- あなたは、ありのままの姿で、すでに美しい。
免責事項
私は心理学や医療の専門家ではなく、診断や助言を行う立場にはありません。
本記事は研究や書籍、筆者の経験をもとにした参考情報です。
内容を鵜呑みにせず、必ずご自身の状況や体調と照らし合わせてお読みください。
もし違和感や不安がある場合は、公認心理師や臨床心理士などの専門家への相談もご検討ください。
具体的な相談先については、ページ下部の相談窓口にも詳しくまとめています。
参考文献
 クロ
クロ







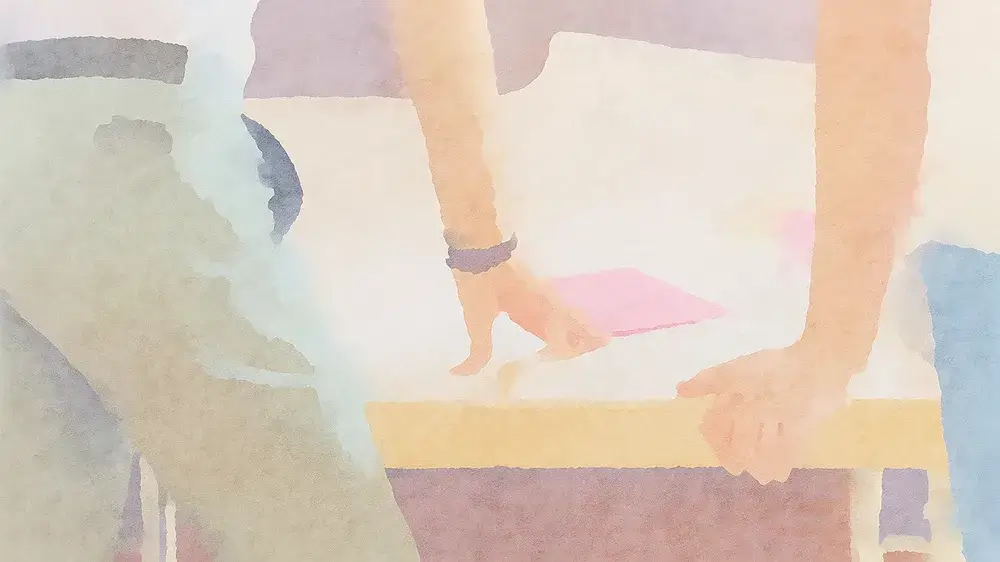
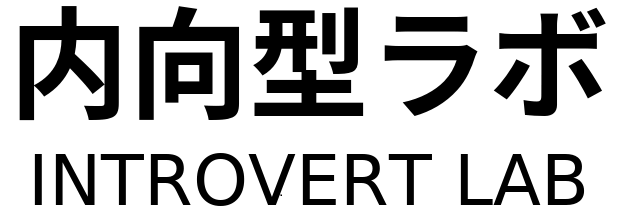





コメント