「犯人はこの中にいます」
ミステリー作品の終盤、探偵はこう宣言する。
ここから始まるのは事件の真相究明であるが、だれがその真相を保証しているのだろうか?
探偵が「皆を集めてさてと言い」はじめてから行われるのは、本当に「真理を突き止める」推理なのだろうか。
否である。推理の披露から始まるのは、真理の追究ではない。
聴衆と犯人、そして自分自身を「納得させる」ための思考の論理ゲームである。
人間の性質を前提にすれば、推理の正しさを保証するのは「証拠」ではなく「納得」である。
ミステリだけではない。人は「真実」に納得するのではなく「整合した物語」に納得したい存在である。
科学、倫理、哲学、歴史の研究家など、どれほど理性的な人であっても、物事を因果関係で説明したがる。
さらに言えば、自分の信念を肯定してくれる物事ほど、人は容易に納得してしまう。
この記事では、人がどれだけ「物語・思考・信念・因果関係」に支配されているかを考えていきたい。
目次
真実は常に「仮説」である
人は、自分の信念や因果に「納得」するためなら容易に真実を捻じ曲げてしまう。
この傾向は、心理学では「前後即因果の誤謬」と呼ばれている。
前後即因果の誤謬
前後して起きた出来事のあいだに、根拠のない因果関係を見出してしまう思考の癖。
事象:試験の前に「新しいお守り」を買ったら、合格した。
誤謬:「お守りを買ったから合格した」と信じる。
真実:合格の主な要因は「勉強量や体調」であり、お守りの購入は直接関係しない。
理性では「お守りは関係ない」と理解していても、感情の面では「無関係にしたくない」という心理が働くこともある。
ミステリにおける「後期クイーン的問題」
前後即因果の誤謬という思考の癖は、ミステリにおける「後期クイーン的問題」を題材にすると、より鮮明に理解できる。
後期クイーン的問題とは
古典的ミステリに見られる「探偵と事件」をめぐる二つの論点の総称。1
20世紀アメリカの推理作家エラリー・クイーンの後期作品に顕著であることから、この名で呼ばれる。
①探偵が提示した最終解決が、本当に唯一の真相であることを作中では完全に証明できない。
②探偵が裁定者のように振る舞い、登場人物の運命を決定づける立場に立つことの是非
①の命題は、たとえば次のように整理できる。(②の命題も面白いが今回は①だけを取り上げる)
探偵が証拠A・B・Cをもとに推理し、犯人Xを導き出した。
しかし、事件を覆す証拠Dが存在しないことまでは証明できない。
また、犯人Xの背後に真犯人Yがいないことも証明できない。
つまり、探偵は証拠A・B・Cから犯人Xを導く推理が「もっともらしい」ことを容疑者に示すことはできる。
しかしそれが、唯一の真相であるとは論理的に確定できない。
探偵の確信は「自分の信念」と隣り合わせであり、因果を結びつける思考は、真実の取り違えを生みかねない。
これら2つの命題は推理小説内部の問題である。
しかし、前後即因果の誤謬という思考の癖を踏まえるなら、決して虚構の中だけの話ではない。
そこから生まれる思考を、私たちは偏見や思い込み、あるいは先入観と呼ぶ。2
農業革命と定住革命の矛盾
ユヴァル・ノア・ハラリの著書『サピエンス全史』では、人類の歴史を決定づけた革命は「3つ」とされている。
人類の3つの革命
1. 認知革命(約7万年前):言語を操り、「虚構(神・伝説・国家)」を信じる能力を得た。
2. 農業革命(約1万2000年前):狩猟採集を離れ、小麦などの栽培を開始。定住生活へ移行。
3. 科学革命(約500年前):「無知の発見」。実験と観察に基づき、自然界を制御し始めた。
ここで取り上げるのは、農業革命とは「農耕のために定住生活を余儀なくされた」という見方である。
定住の理由を、狩猟採集民から農耕民への移行に求めると、たしかに「もっともらしい」理由である
しかし、この考え方は日本の歴史を見るだけで揺らぐ。日本では農耕と定住が逆転するのだ。
日本人が本格的な農耕生活を始めたのは弥生時代(紀元前4世紀頃〜3世紀頃)とされている。
しかし、縄文時代(約1万6500年前〜前4世紀頃)には、すでに一定の定住生活が営まれていた。
この事実だけでも、農業→定住という因果が「必然」ではないことが分かる。
この定住革命説について興味深い議論を展開しているのが、國分功一郎『暇と退屈の倫理学』である。3
食料生産を前提とする見方は、よく知られた事実(たとえば縄文時代の人々は定住していたが農耕を行っていなかった)を考え直してみるだけですぐに崩れてしまう、もろい偏見なのである。
國分功一郎『暇と退屈の倫理学』第二章「暇と退屈の系譜学」より
國分功一郎は「暇と退屈の系譜」を考察するために定住革命説を選び取っている。
しかしここでもまた、因果が確定したかのように語られる構図が生まれている。4
縄文時代にも栗や豆の管理的利用が行われていた可能性がある。
あるいは、農業と定住が「別の理由」で同時期に進行しただけなのかもしれない。
この2つの説から言えるのは、人類史の約1万5000年前後に「大きな変化」があったらしい、ということだけである。
どちらが「確定的か」というのは、もはや信念の問題といえる。
成功者の習慣と「生存者バイアス」
「成功者は早起きしている」「なぜ私が成功できたのか」
少し調べるだけで、成功者にまつわる話は山のように見つかる。
私の身近にも、「ニッチなジャンルでなぜ成功したのか」と、その「なぜ」を語る人物がいる。
成功した人は、「成功の秘訣」を知っているから成功したのだろうか。
違う。彼らは「成功の秘訣」を語っているのではなく「成功の物語」を語っているのである。
なぜなら、誰も「成功の秘訣」そのものを事前に知ることはできないからだ。
成功者とサイコロ
100人が集まっている会場で、全員にサイコロが配られる。
まず『5』の出目が出た人だけが残る。確率的に約17人が残る。
次も『5』の出目が出た人だけが残る。確率的に約3人が残る。
残った数人が、サイコロのゲームで勝ち残れた「もっともらしい」理由を語り出す。
このサイコロには、自分の性質、環境、運、時間、関係性など、あらゆる要素が含まれている。
つまり「予測できないサイコロ」である。予測できると豪語するのはラプラスの悪魔くらいだろう。
冷静に考えれば『サイコロで5を出す方法』など分かるはずがない。だから成功者は自分の人生を語るしかない。
人の思考は因果関係を好むため『サイコロで5を出せた理由』を後から作り出して自分も他者も騙す。
これは「生存者バイアス」もしくは「後知恵バイアス」と呼ばれる。
たまたま残った人だけが可視化され、その人たちが「成功の秘訣」を知っているかのように見えてしまう現象である。
それを真似しても、自分とは性質も環境も時間も関係性も異なるのだから、同じ結果になる保証はどこにもない。
もしかしたら「5を出せた理由」が「真実」かもしれないが、それを確認する術も存在しない。
たとえば、投資の神様と言われるウォーレン・バフェットと呼ばれる人物がいる。
同じ時代に似た思考を持ち、ほぼ同じ方法を実践して「投資の神様」になれなかった人がいる可能性は否定できない。
科学は信頼できるのか?
現在、もっとも「真実」に近づく方法の一つが科学だと言われている。
しかし、その科学でさえ、「絶対」という言葉を用いることはほとんどない。
なぜなら反証可能性――誤っている可能性を指摘できる構造――を備えていることが、科学の条件だからである。
科学とは「暫定的な真理」を更新し続ける営みである。ゆえに「最良」なのは間違いないが、万能ではない。
科学と「再現性の危機」
現在の科学、とくに心理学では「再現性の危機」と呼ばれる問題に直面している。5
ハンス・アイゼンクの研究には、多数の不正や深刻な疑義が指摘されている。
「老人」という言葉を聞くと歩行速度が遅くなるとする研究は、その後の検証で再現が困難とされた。
幸福度調査も、その瞬間の気分や直前の出来事に大きく左右される可能性がある。
なぜこのような事態が起きるのか。それは研究を取り巻く「環境」に目を向ければ理解できる。
研究者は大学や公的機関から研究費を得ており、論文が採択されることが評価や資金に直結する。
大学側にとっても、成果を上げられない研究者を長期的に抱えることは難しい。
さらに科学者にとっては、自らの仮説が世間に認められることは大きな名誉でもある。
その結果、研究者は「結果を出さなければならない」という強い圧力にさらされる。
たとえ意図的でなくとも「自分の仮説は正しいはずだ」という思い込みにとらわれれば、解釈は容易に歪む。
その典型例が、望ましい結果が得られるまで分析を繰り返す、いわゆるp値ハッキングである。
好きな目が出るまでサイコロを振る
p値ハッキングとは、要するに「仮説を支持する数値が出るまでサイコロを振り続ける」ような行為である。6
p値ハッキング
研究結果に「相関がある」と示せる有意水準にわずかに届かないときに行われる行動。
分析条件を変えたりデータを追加したりして、数値が基準を超えた時点で実験を終える。
また「相関に近い傾向が見られた」などの表現で、結果を過度に肯定的に解釈することもある。
これは意図的にも、無自覚的にも起こり得る問題である。
さらに「望ましい結果が出た研究だけを論文化して否定的な結果は公表しない」心理を「出版バイアス」と呼ぶ。
出版バイアス
たとえるなら、学生が「良い点数」だけを親に見せて「悪い点数」のテストの存在自体を隠す手法。
これは複数の研究を統合して検討するメタ分析においても、否定的な結果が過小評価される危険が生じる。
加えて、心理学や社会科学のデータは「西洋的・高学歴・産業化・富裕・民主的」な社会に偏っている場合がある。
これは「WEIRD問題」と呼ばれる。
当然ながら、そのデータは特定の社会と時代の基準であって「人類全体の基準」ではない。
知性と名誉と「確証バイアス」
頭のよい人物は「思考の癖」やバイアスに呑まれないのだろうか。
残念ながら、頭が良くても人である限りバイアスから完全に逃れることはできない。
むしろ、経験の浅い子どものほうが「先入観」にはとらわれにくい場合もある。
経験を重ねることで、人は「世界を予測する能力」を獲得していく。
裏を返せばその予測が枠組みとなり、思考を方向づける。子どもは未知に対してより開かれている。
数学における「1+1=2」という答えに、「なぜそうなるのか」と改めて問うことは、大人には生じにくい。
家族が突然「空を飛んだ」としたら、大人は恐怖するかもしれないが、子どもは興奮するかもしれない。
「1+1=2」を自明のものとして疑わない知性は効率的である。しかし同時に、新しい可能性を閉ざす檻にもなり得る。
空飛ぶ家族に恐怖する大人は「人は空を飛ばない」という「自分の世界のルール」が崩れることを恐れている。
一方、子どもにとって世界は、まだ解釈の定まっていない「可能性の塊」である。
ゆえに、知能や知性の高い人は「世界のルールを構築する力」「論理を組み立てる能力」に優れている。
しかしその能力は、真実とは無関係に、無自覚に、自らの信念を正当化する論理を構築する方向にも働き得る。
強固な「世界のルールを構築する力」が「自らの正当性を証明する根拠」になってしまう。
強固であるが故に、誰もその信念を崩すことができない。
それは、もっともらしい理由で相手を「論破」する力であり、事実とは必ずしも一致しない弁論術でもある。
あなたは間違っている。なぜなら世界は○○であり、○○だからである。
地位や名誉がある人ほど過去に積み上げた『資産』を守るために、バイアスはより強固なものへと変貌する。
不確かな世界をどう生きるべきか
ここまで、私たちは真実について「存在するかもしれないが確定はできない」という事実を確認してきた。
ではこの不確かな世界を、どのように生きるべきなのだろうか。
「因果」というメガネを意識する
人は物事を因果的に、すなわち物語として理解する。それは生存に有利に働いてきたからである。
あそこの崖は岩盤が脆い → 崩れるかもしれない
川の近くに猛獣らしき足跡があった → 猛獣がいたのだろう。
あの人は好意的に接してくれる → 優しい人だろう
このように、因果で世界を把握する能力は生存に役立つ。
一方で人間は、フィクションという「架空の物語」や、論理的に破綻している物語すら楽しむことができる。
たとえば「過去へのタイムスリップ」「異世界転生後の記憶保持」など。
それでも私たちは、その物語を成立したものとして受け入れて楽しむことができる。
つまり「因果的に考える」ことと「真実である」ことは必ずしも一致しない。
この「因果のメガネ」を完全に外すことはできない。できるのは、それをかけていると自覚することだけである。
だからこそ私たちは「前後即因果の誤謬」や「確証バイアス」に陥っていないか、立ち止まって問い直す必要がある。
少なくとも、それは人間関係や善悪、倫理的な判断においては有用に働く。
あわせて読みたい
認知バイアスとは?|人が誤解する理由を心理学で解説【15選】
なぜか私は理解されない —— 誰もが1度はそう感じたことがあるのではないだろうか? また、人は他人を「タイプ」で当てはめて理解してしまうことも少なくない。 なんで分…
懐疑と選択|すべてを疑えば足は止まる
根拠のない推論や、感情に基づく判断を疑う姿勢を「懐疑主義」という。
これは紀元前の西洋哲学にまで遡る考え方(スケプティコス派)だが、現代においてもなお有用に働く。
懐疑主義
客観的な「確信」を疑い、判断を保留する生き方。その方法は「エポケー(判断停止)」とも呼ばれる。
現象をありのまま観察し、何が真実かを確定しない態度。
思考をいったん脇に置き、今この瞬間に集中する「マインドフルネス」も、ある意味ではエポケーに通じる。
懐疑主義的な思考は現代でも有効だが、「ありのままを観察する」科学もまた絶対ではない。
私たちは因果という「認識のメガネ」を通して世界を見ている。
理性も感情も完全には信用できない以上、物事を本当に「ありのまま」に捉えることは不可能である。
しかし、現象も科学も理性も感情もすべて信用できないとするならば、それは懐疑主義を超えて虚無主義(ニヒリズム)に至る。
虚無主義に支配された人生は、言うまでもなく活力を失う。生きる意味すら信用できないのだから。
だからこそ私たちは、疑い続けながらも、自らの信念によって「何か」を選択しなければならない。
不完全さを認めた上での「決断」
この記事で導いた結論は、次のとおりである。
人は「因果」という枠組みで世界を理解する「認識のメガネ」を掛けている。
理性・感情・信念から導き出される「真実」は、人それぞれの思考の癖によって少なからず歪められている。
それでも何かを選び、自らの信念を持たなければ、人はニヒリズムへと傾く。
前述で引用した、『暇と退屈の倫理学』においても、「定住革命」という1つの立場が提示されている。
この立場に反証を試みるならば、同じ土俵(農耕革命と定住革命の選択)から議論する必要がある。
そのうえで、選択そのものを否定する権利は誰にもない。(1万5000年前の人類を連れてこれたとしても)
たとえば、神の存在も完全に否定することはできない。(宗教的教義ではなく世界や宇宙の創造主としての存在)
進化論や宇宙論で「仮説」を説明できても、その「始まり」そのものを確定することはできないからだ。
ゆえに私は、神の存在を「不可知」と位置づけ、これ以上の断定を控えるという選択をしている。
神を信じるのも選択であり、信じないのも選択である。いずれも絶対的な「真実」とは言い切れない。
だからこそ、人生とは「不確かさを引き受けた決断」の連続なのだと、私は考えている。
まとめ|人は物語る生き物である
ミステリの探偵も、歴史を語る研究者も、成功を語る起業家も、科学者も、そして私たち自身も含めて。
証拠やデータや理性を用いながら行っているのは「真理の保証」ではなく、もっともらしい物語の構築である。
人は因果で世界を理解する。そこから逃れることはできない。
だからこそ、前後即因果の誤謬や確証バイアス、生存者バイアスが生まれる。
科学も暫定的で、歴史も解釈であり、成功談も物語である。
真実は常に仮説であり、私たちは仮説の上で生きている。
それでも選ばなければならない。信じなければならない。決断しなければならない。
猫は網膜に「赤」を感知する錐体細胞を持たないため、猫にとって赤色は存在しない。
人間も同様に「世界の真実」を認識、推測するための「何か」が存在しない可能性がある。
完全な確実性が訪れる日は来ない。もっとも確実性の高い数学でさえ不完全性定理により限界がある。
だから人生とは、不完全さを自覚したうえで、それでも物語を引き受ける営みなのである。
免責事項
本記事は筆者個人の思想的立場を整理したものです。
特定の宗教・科学理論を否定または肯定する意図はありません。
内容を鵜呑みにせず、ご自身の感覚を大切にしながらお読みください。
参考文献と注釈
 クロ
クロ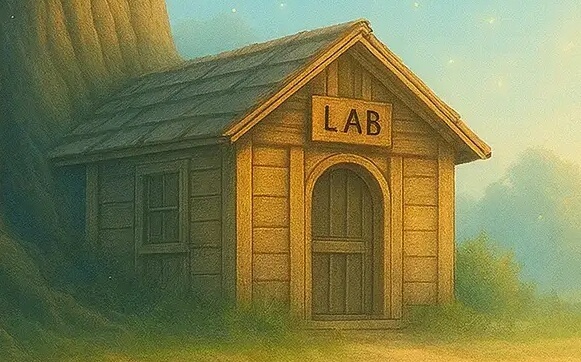
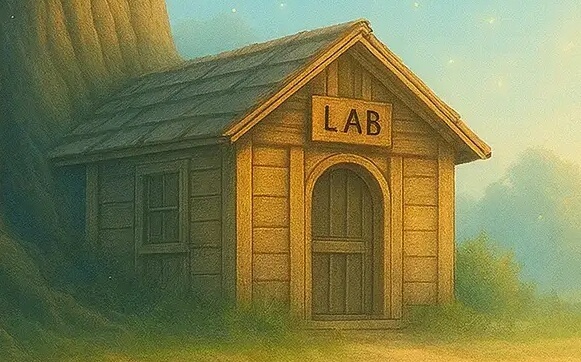







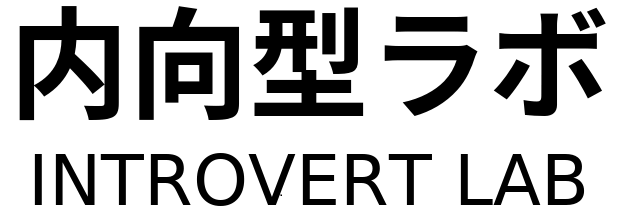

コメント