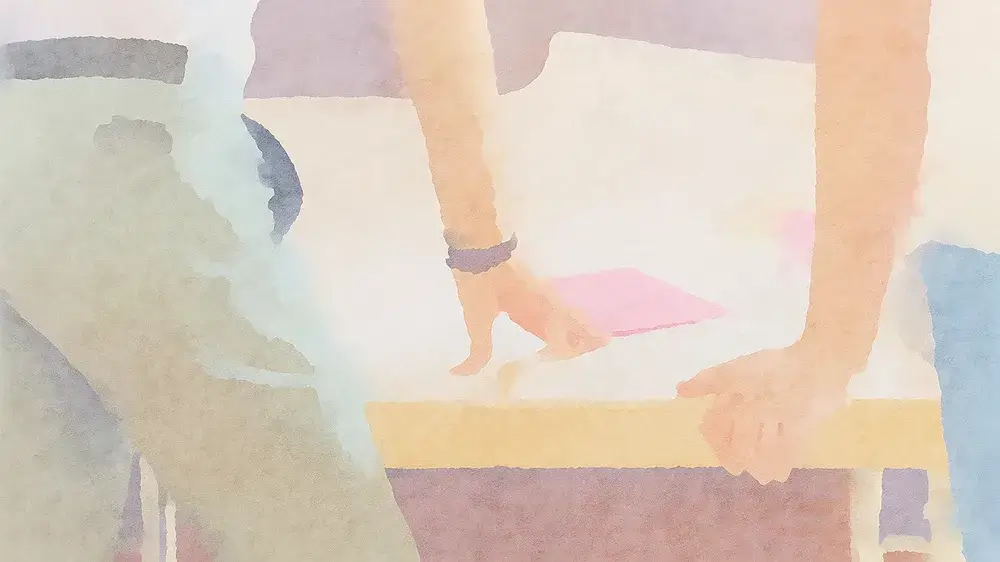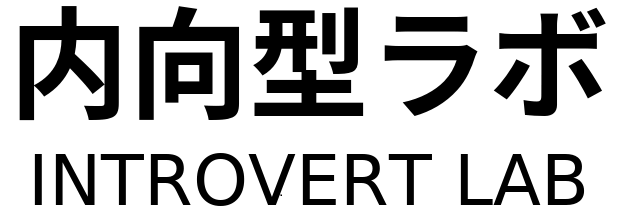このページでは「内向型ラボ」の主要な参考文献をまとめています。
このページの文献マークについて
文献ごとに「難易度」マークで示しています。
📗 入門 … 初めての人でも気軽に読めるやさしい入門書。
📘 中級 … 集中して読めば理解できる標準的な中級書籍。
📙 上級 … 専門的または抽象的で、粘り強さが必要な本。
ここで紹介する本は運営者が必ず一読し、記事作成の引用や、自身の思想に影響を与えたものです。
目次
【自己理解】自分の「特性」を知る
内向型の基礎
【内向型を強みにする おとなしい人が活躍するためのガイド】📘
マーティ・オルセン・レイニー(著)務台夏子(訳) パンローリング:2013年
内向型を知る入門書に最適。基本的な情報から科学的な知見。生活の応用まで広く書かれている。
【内向型人間のすごい力 ─ 静かな人が世界を変える】📘
スーザン・ケイン(著)古草秀子(訳)講談社:2015年
内向型の価値を社会に広めたベストセラー。科学的な知見の外、内向型の社会の役割を明確にした本。
【「静かな人」の戦略書:騒がしすぎるこの世界で内向型が静かな力を発揮する法】📘
ジル・チャン(著)神崎 朗子(訳)ダイヤモンド社:2022年
内向型が社会で活躍するための「実践的な戦略書」特性を活用した具体的な行動方法が論じられている。
HSP/高い感受性と研究
【HSPブームの功罪を問う(岩波ブックレット 1074)】📗
飯村修平(著)岩波書店:2023
近年広まった「HSP」という概念を、心理学者の視点から冷静に分析する一冊。誤解や商業化による弊害にも切り込み、HSP像を再考させてくれる。
【敏感すぎる私の活かし方 高感度から才能を引き出す発想術】📘
エレイン・N・アーロン(著)片桐恵理子(訳)パンローリング:2020年
作者がHSP提唱者の邦訳版。しかも最新の知見まで含んだ改訂版でもある。HSPに関して一冊を選ぶならこちら。
【傷つきやすいのに刺激を求める人たち】📘
トレイシー・クーパー(著)長沼睦雄(監)時田ひさ子(監)喜多直子(訳)
HSPの中でも、HSS型(刺激追求性)HSPに焦点を当てた本。特性論などの科学的根拠にも触れた骨太な一冊
【HSP研究への招待:発達、性格、臨床心理学の領域から】📙
飯村周平(編集)/上野雄己/小塩真司/岐部智恵子/串崎真志/髙橋亜希/平野真理/矢野康介(著)|花伝社:2024年
研究者8名が結集し「高い環境感受性」を持つ人の最新研究動向を総覧。30年にわたる心理学研究を踏まえて「HSPを心理学者はどう捉えているのか」を整理している。
特性論/性格を連続に捉える
【パーソナリティを科学する ─ 特性5因子であなたがわかる】📘
ダニエル・ネトル(著)竹内和世(訳)白揚社:2009年
心理学で現在もっとも広く受け入れられている性格モデル「ビッグファイブ」を分かりやすく解説した一冊。因子分析という統計的手法がどんな特徴を捉えるのかを理解できる。
【Big Fiveパーソナリティ・ハンドブック 5つの因子から「性格」を読み解く】 📙
谷伊織・阿部晋吾・小塩真司(編著)福村出版:2024年
ビッグファイブ研究の歴史から最新の知見までを網羅した決定版。理論的基盤・実証研究・応用まで広くカバーしており、学術的にも信頼性が高い一冊。
類型論/性格を分類する
【16性格診断は嘘をつく: MBTIを他者理解の武器にする方法】📗
かずし校長(著)個人出版(Amazon):2025
「MBTIへのいざない」を一般読者向けにかみ砕き、SNSで流行する16タイプ診断との違いを整理。図解や事例が豊富で入門に最適。
【MBTIへのいざない ユングの「タイプ論」の日常への応用】📘
R.R.ペアマン・S.C.アルブリットン(著)岡田由紀(訳)
共有言語として有名なMBTIを丁寧に解説。この本では「診断ツール」ではなく「自己理解と他者理解のための枠組み」としての意義が示される。
【ユング心理学入門〈心理療法コレクション I〉】📙
カール・グスタフ・ユング(著)河合隼雄(訳)創元社:2009年
ユング心理学の定番入門書。性格類型の基盤になった考え方を学べる。かなり難しいが一章だけでも読む価値がある。
【人類を科学】脳と進化の心理学
人類史と進化論
【サピエンス全史 文明の構造と人類の幸福】📙
ユヴァル・ノア・ハラリ(著)柴田裕之(訳)河出書房新社:2016年
文明の発展を描く名著。少々長いが、深い思索に長けた内向型が果たしてきた役割を考えるきっかけにもなる。
【利己的な遺伝子〈40周年記念版〉】📙
リチャード・ドーキンス(著)日髙敏隆・岸由二・羽田節子・垂水雄二(訳)|紀伊國屋書店:2018年
進化の主役は個体ではなく「遺伝子」であるという視点から、生物の行動や協力・利他性を再解釈した名著。
脳と心の理解
【多動脳 ─ ADHDの真実】📘
アンデシュ・ハンセン(著)久山葉子(訳)新潮新書:2025年
ADHDは「欠陥」ではなく、進化の過程で生まれた人類の多様性の一形態。「探索と創造の力」を読み解く希望の一冊。
【脳と心のしくみ(大人のための図鑑)】📘
池谷裕二(監修) 学研プラス:2015年
神経伝達、感情、記憶、意識などのメカニズムを写真とイラストで直感的に理解できる。脳と心の全体像をつかむ入門書として最適。
【だれもわかってくれない ─ 傷つかないための心理学】📘
ハイディ・グラント・ハルヴァーソン(著)高橋由紀子(訳)早川書房:2020年
自己啓発本に見えて実は違う。「認知のクセと脳の仕組み」を網羅的に分かりやすく解説してる実践的心理学書。
【こころ検定2級 公式テキスト(精神解剖学基礎・精神医科学基礎・心理カウンセリング基本技能)】📘
2024年(メンタルケア心理士講座教材)※本書は市販されておらず、「メンタルケア心理士講座」受講者向け教材として配布されています。
心理学とカウンセリングの基礎を体系的に学べる公認教材。身体・医学・薬学・メンタルまでを横断的に扱い、心のしくみを総合的に学べる。
【Science Fictions あなたが知らない科学の真実】📙
スチュアート・リッチー(著)矢羽野 薫(訳)みすず書房:2024年
再現性、統計の誤用、出版バイアスなど、現代科学が抱える問題を実例とともに検証する1冊。私たちがどう科学に向き合うべきかを示してくれる。
【ファスト&スロー(上・下)】📙
ダニエル・カーネマン(著)村井章子(訳)早川書房:2012年
人間はなぜ非合理な判断をしてしまうのか。もはや定番なった「人の思考のクセ」を理解するのに欠かせない名著。
【新・動機づけ研究の最前線】📙
上淵寿・大芦治(編著)/西村多久磨・篠ヶ谷圭太・稲垣勉・梅﨑高行・利根川明子・鈴木雅之(著) 北大路書房:2019年
達成目標理論や自己決定理論など、主要な動機づけ理論の発展を体系的に整理した学術書。
【フロー体験 ─ 喜びの現象学】📙
M.チクセントミハイ(著)今村浩明(訳)世界思想社:1996年
深い集中と没頭の中で感じる幸福「フロー」の現象を心理学的に解き明かした名著。創造性や生きがいの本質に迫る。
【自己受容と習慣】心地よい暮らし
幸福とメンタルケア
【わたしが「わたし」を助けに行こう ― 自分を救う心理学 ―】📗
橋本翔太(著) 単行本:2024年
人はつらさを感じると、無意識に自分を否定してしまう。自己否定を回復と自己理解へと変換するための実践書。
【実践 ポジティブ心理学 ─ 幸せのサイエンス】📗
前野隆司(著)PHP新書:2017年
「幸福とは何か」を科学的に探究するポジティブ心理学の実践書。日本人に最適化された分析はとても参考になる。
【ウェルビーイング】📘
前野隆司・前野マドカ(著)日本経済新聞出版:2022年
幸福を「満足度」ではなく「良い状態の持続」として捉える入門書。個人よりも社会全体に焦点があたっている。
【悲しみの力 ―「悲しみ」と「切なる思い」が私たちを健全な人間にする】📘
スーザン・ケイン(著)古草秀子(訳)ディスカヴァー・トゥエンティワン:2023年
ネガティブな感情を、ネガティブのまま前向き活かす力に変える。内向型の旗振り役による「新時代の幸福論」
【セルフ・コンパッション[新訳版] 有効性が実証された自分に優しくする力】📘
クリスティン・ネフ(著)石村郁夫・樫村正美(訳)金剛出版:2021年
自己批判をやめるのではなく、自分に優しく接することで回復力や挑戦を持続させる。
【ポジティブ心理学の挑戦 “幸福”から“持続的幸福”へ 】📙
マーティン・セリグマン(著)宇野カオリ(訳)ディスカヴァー・トゥエンティワン:2014年
ポジティブ心理学の創始者による理論書。持続的幸福(ウェルビーイング)という新しい概念を提示する。
【孤独の本質 つながりの力 ― 見過ごされてきた「健康課題」を解き明かす】📙
ヴィヴェック・H・マーシー(著)樋口武志(訳)飛鳥新社:2023年
孤独は心と身体に影響する社会的な健康課題。科学的データや歴史、体験を交えて「つながりの力」を語る。
習慣とフィジカルヘルス
【世界の最新メソッドを医学博士が一冊にまとめた 最強脳のつくり方大全】📘
ジェームズ・グッドウィン(著)森嶋マリ(訳)文藝春秋:2024年
脳とあるが実際は心身の健康大全、科学的根拠と網羅性は随一。長いけどこれ一冊で健康博士になれる。
【運動脳】📘
アンデシュ・ハンセン(著)御舩由美子(訳)サンマーク出版:2022年
運動が脳を強化する科学を解説。インドア趣味が多い内向型にも取り入れやすい、集中力・メンタル向上の実践知。
【睡眠こそ最強の解決策である】📘
マシュー・ウォーカー(著)櫻田潤・桜田直美(訳)SBクリエイティブ:2018年
睡眠研究の第一人者による名著。眠りの仕組みと生活改善の関係。疲れやすい内向型にこそ役立つ「休息の教科書」
【EAT 最高の脳と身体をつくる食事の技術】📘
ショーン・スティーブンソン(著)花塚恵(訳)ダイヤモンド社:2022年
栄養学と科学的研究を土台にした、食事で脳と身体を最適化する方法。食と健康の関係を体系的に学べる一冊。
暮らしの基盤と経済
【漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則】📗
ジョージ・S・クレイソン(著)坂野旭(漫画)文響社:2019年
お金とはなにか。その本質を、古代バビロニアの少年の成長物語と重ねて描く寓話的ストーリー。
【本当の自由を手に入れるお金の大学】📗
両@リベ大学長(著)朝日新聞出版:2024年
現代日本で「お金を味方にする」生き方を築く指南書。家計・投資・稼ぎ方を実践的に学ぶことができる。
【きみのお金は誰のため ─ ボスが教えてくれた「お金の謎」と「社会のしくみ」】📘
田内学(著) 東洋経済新報社:2023年
数字や資産ではなく「なぜ働くのか」「何のためにお金を使うのか」を考えさせてくれる現代の教養書。
【サイコロジー・オブ・マネー ─ 一生お金に困らない「富」のマインドセット】📘
モーガン・ハウセル(著)児島 修(訳)ダイヤモンド社:2021年
お金に対して「どう振る舞うか」に焦点を当て、再現性のない成功談や数字至上主義への距離の取り方を示す。
【アート・オブ・スペンディングマネー ─ 1度きりの人生で「お金」をどう使うべきか?】📘
モーガン・ハウセル(著)児島 修(訳)ダイヤモンド社:2025年
お金を「増やす技術」ではなく「どう使えば後悔が少ないか」という視点から捉え直す1冊。
【敗者のゲーム〈原著第8版〉】📙
チャールズ・エリス(著)鹿毛 雄二・鹿毛 房子(訳)日本経済新聞出版:2022年
投資の世界では、プロ同士が「勝とうと競い合う」行為そのものが失敗を招く。という逆説を示した名著。
【ウォール街のランダム・ウォーカー〈原著第13版〉──株式投資の不滅の真理】📙
バートン・マルキール(著)井手 正介(訳)日本経済新聞出版:2023年
インデックス投資の合理性を歴史、ブーム、数学、統計から示す。約50年前から続く古典的名著。
【魂の回復】孤独の中で深く思索する
生き方を思索する
【マンガ 老荘の思想】📗
蔡志忠(作画)和田武司(訳)野末陳平(監修)講談社:2021年
道教思想の根本「老子・荘子」をマンガでやさしく解説。内向型に通じる思想を親しみやすく学べる一冊。
【夜と霧(新版)】📘
ヴィクトール・E・フランクル(著)池田香代子(訳)みすず書房:2002年
ナチスの強制収容所という極限状況の中で、絶望の底で希望を見出す実存の哲学。心を照らす不朽の名著。
【幸福について】📘
ショーペンハウアー(著)鈴木芳子(訳)光文社古典新訳文庫:2013年
「人は幸福になるために生きている」という考えを真っ向から否定した逆説の実践的な幸福論。
【読書について】📘
ショーペンハウアー(著)鈴木芳子(訳)光文社古典新訳文庫:2018年
「自分の頭で考える」ことの重要性を説いた1冊。本を読んだ後に「どうするべきか」の視点をくれる。
【ユダヤ人の成功哲学「タルムード」金言集】📘
石角完爾(著)集英社:2012年
ユダヤ人の根幹をなす口伝律法「タルムード」に由来する説話を通して、思考法・判断基準・生存戦略を読み解く。
【善悪の彼岸】📙
フリードリヒ・ニーチェ(著)中山 元(訳) 光文社古典新訳文庫:2009年
「善/悪」という枠組みを疑い、西洋哲学と道徳を解体する思想書。行間を読む姿勢が求められる難解な書物。
【道徳の系譜学】📙
フリードリヒ・ニーチェ(著)中山 元(訳)光文社古典新訳文庫:2009年
「善/悪」といった道徳概念の起源をたどり、弱者の怨恨から生まれた「奴隷道徳」を暴き出す思想書。
【ツァラトゥストラ(上・下)】📙
フリードリヒ・ニーチェ(著)丘沢静也(訳)光文社古典新訳文庫:2010年
ニーチェ自身が「人類への最大の贈り物」と称した哲学詩。比喩が多く、事前知識なしでは誤読のリスクが高い。
物語に学ぶ
【星の王子様】📗
サン=テグジュペリ(著)河野万里子(訳)新潮社:2006年
子どもの本と思われがちだが、大人こそ読むべき寓話。物事を「目ではなく心」で見る必要性を説く。
【アルジャーノンに花束を〔新版〕】📘
ダニエル・キイス(著) 小尾芙佐(訳) ハヤカワ文庫:2015年
世界は必ずしも優しくない。「賢さと幸せ」は一致しないという事実を、感情レベルで理解させてくれる。
【現代語訳 舞姫】📘
森 鴎外(著)/井上 靖(訳) ちくま文庫:2006年
近代日本文学の原点ともいえる自己葛藤の物語。論理と感情、出世と愛の衝突が明確に浮かび上がる。
【レ・ミゼラブル(上・下)】📙
ヴィクトル・ユゴー(著)永山篤一(編集)角川文庫:2012年
ロマン主義の極致。角川文庫は要点を押さえた要約版。人の「正しさ」とはなんなのだろうか。
【外部リソース】専門・理論サイト
What Is Employee Wellbeing?(統計的ウェルビーイング:ギャラップ社公式)
Theory of Positive Disintegration(TPD)(積極的分離理論:研究者によるアーカイブ)
Oregon Research Institute(ORI)(ビッグファイブ:IPIP公式)
免責事項
本の紹介内容は運営者の個人的な理解に基づくものであり、医学的診断や専門的助言に代わるものではありません。
 クロ
クロ