「自分はなんてダメな人間だろう」―― そう感じたことが、一度はあるのではないだろうか。
- 何をやっても失敗してしまう
- 自分には取り柄なんてない
- 人より劣っている気がする
こうした思いは病理とは関係なく、誰にでも起こりうる「人間的な感情」だ。
失敗や比較、孤独――そうした経験が、私たちを容易に自己否定へと導いてしまう。
特に、内向型の人は思索に耽る時間も多いため反芻思考(辛い経験を何度も思い返すこと)にも陥りやすい。
けれども、もしそのネガティブな感情ごと、自分をまるごと受け入れられたなら?
きっと、少しだけでも前を向けるはずだ。
- どんなときも、自分に優しくする
- 誰もが苦しみを分かち合う存在であると知る
- 「今、この瞬間の自分」に気づく
実際に有効性が科学的に示され、臨床現場でも用いられている「自分を受け入れるための心理学」が存在する。
それが、セルフコンパッション(Self-Compassion)である。
✅この記事の概要
- セルフコンパッションとは何か――「自分に優しくする心理学」の基礎を学ぶ
- 「甘やかし」との違い、自尊心との関係を理解する
- 3つの要素(優しさ・共通の人間性・マインドフルネス)を具体例で体感する
- 内向型の人にセルフコンパッションが特に必要な理由を知る
- 日常で実践できるセルフコンパッションの方法を紹介
- 筆者の実体験から学ぶ――「弱さを受け入れることは強さになる」

この記事では、クリスティン・ネフ博士の著書を参考にしています。1
また、心理学の知見を個人の自己理解に役立てることを目的としています。
そのため、学術論文の厳密な解説や、専門家としての助言を行うものではありません。
目次
セルフコンパッションとは
セルフコンパッションとは、アメリカの心理学者クリスティン・ネフ博士が提唱した「自分に優しくする心理学」である。
「自分を責めない」という発想の転換
コンパッション――思いやり。それは、ふつう他者に向けられるものだと考えられがちだ。
しかし、他人には優しくできても、自分には優しくできないという人は少なくない。
他者に優しくできても…
- 人の失敗には寛容でも、自分のミスは許せない
- 他人には励ましの言葉をかけられるのに、自分には厳しい
- 「優しくすれば甘えるだけ」と思い込み、無意識に自分を追い詰める
セルフコンパッションは、そんな「思いやりの矢印」を自分にも向ける行為だ。
つまり、苦しんでいる自分を、否定せず、温かく受け止める力のことを指す。
セルフコンパッションの基本
- 失敗しても、自分を責める理由にはならない
- 誰もが間違える。それは人間として自然なこと
- どんな状況でも、自分に対して思いやりを持つ
セルフコンパッションとは、自分を甘やかすことではなく、現実を優しく受け入れる勇気である。
「甘やかし」とは違う
「自分に優しくする」という考え方は、どうしても「甘え」や「怠け」と誤解されやすい。
しかし、セルフコンパッションは決して甘やかしではない。
セルフコンパッションは「自分を叱咤して奮い立たせる」こととは対極にある。
なぜなら、過度な厳しさは自分を萎縮させ、挑戦する力を奪ってしまうからだ。
- 次は失敗しないようにしなければならない
- 人より劣っているのだから、もっと努力しなければ
- 次こそは…次こそは…次こそは…
このような思考は一見ストイックに見えるが、実際には自分を追い詰め、成果を下げ、自己批判の連鎖を生む。
やがて人は「失敗したくない」という恐れから、失敗したときの言い訳を準備しはじめる。
心理学ではこれをセルフ・ハンディキャッピングという。
セルフ・ハンディキャッピングとは
失敗を前提に、言い訳ができるようにわざと手を抜く行為
たとえば勉強する時間があるのに、あえて予定を詰め込む
そしてこう言う「時間がなかったから仕方ない」
もちろん、セルフコンパッションを言い訳として使えば、同じように前進を妨げてしまう。しかし、それは本来の意味を誤解しているからだ。
セルフコンパッションとは、「自分を甘やかすこと」ではなく、自分を、そして他者を深く尊重することである。
誰だって失敗するニャ。大事なのは、責めずに次の糧にすることニャ。
自尊心との違い|優劣から理解へ
また、高い自尊感情、高い自尊心とセルフコンパッションは関係しているが、焦点の当て方が違う。
自尊心を持つことは良いことに思えるかもしれない。少なくとも幸福感を覚えることができるからだ。
しかし、高い自尊感情が、学業成績や職務上の業務、指導スキルを高めることはない。
子供においても、自尊感情と非行を防止することもなかった。という研究もある。
さらには高い自尊感情はナルシシズム(過剰な自己愛)傾向とも関連が指摘されている。
ナルシシズム的な思考は、しばしば次のような心の声として現れる。
- 自分は優れている
- 他者よりも上に立っている
- だから私は正しいのだ
一見すると自信に満ちているようだが、これらの思考は「他者と比べることでしか自分の価値を確認できない」危うさをはらんでいる。
もっと言えば、自尊感情と本人の資質は無関係であるとも言われている。
クリスティン・ネフ博士も、著書で自尊感情の高さと「はだかの王様」を関連づけている。
自尊感情は「他者との優劣」も無意識に関係している。人間の優劣をセルフコンパッションは否定する。
天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず…ニャ。
そして、セルフコンパッションを実践すれば、自己も他者も受け入れた、健全な自尊感情が育つ。
セルフコンパッション|3つの要素
では、具体的にセルフコンパッションとは何をすればいいのか? その中身を見ていこう。
セルフコンパッションは、基本的に3つの要素で構成されている。
自分への優しさ(Self-Kindness)
まず一つ目は「自分に優しくすること」だ。
「そんなのもう出来ている」と思う方もいるかもしれない。
しかし、セルフコンパッションの「優しさ」とは、状況にかかわらず自分を責めないことだ。
失敗した自分も、情けない自分も含めて――どんなときでも、受け入れてあげる姿勢を指す。
たとえば、寝坊して会社に遅刻しそうになっている場面を想像してみよう。焦らない人はほとんどいないはずだ。
寝坊した。早くしないと遅刻してしまう。
急いでいるせいで水をこぼした。足の小指をぶつけた。さらにイライラしてしまう。
ああ今日は残業だ、謝罪もしないといけないし、めんどくさい。
なんで昨日の自分は早く寝なかったんだろう。
セルフコンパッションを実践すると、同じ状況がこう変わる。(「自分への優しさ」の部分をオレンジで表示)
寝坊してしまった。会社に遅刻してしまう。
でも、普段より長く眠れたおかげで少し体が楽だ。
遅刻してしまうのは仕方ない。 まずは連絡して、あとで埋め合わせをしよう。
残業になっても、今日は違う時間に帰れる。気分を変えるチャンスかもしれない。
せっかくだから、普段寄らないカフェにでも立ち寄って帰ろう。
もちろん、会社や同僚、上司への謝罪は当然のこととして、普段から遅刻をしない心がけは前提だ。
それでも、確実に後者のほうが心に優しく、前向きな一日を取り戻せる。
「遅刻をしない」は次の〈共通の人間性〉にもつながるニャ。
共通の人間性(Common Humanity)
二つ目は「共通の人間性」――誰もが不完全であり、失敗する存在だという理解だ。
私たちは、苦しいときほど「なぜ自分だけが」「自分ばかり損をしている」と感じてしまう。孤独感は、痛みをさらに増幅させる。
しかし、セルフコンパッションでは、その孤独な視点をそっと広げる。
「これは人間である以上、誰にでも起こりうることなんだ」――そう気づくことこそが、共通の人間性である。
たとえば、仕事でミスをして落ち込んでいる場面を想像してみよう。
なんで自分だけこんなに失敗するんだ。
周りはみんなうまくやっているのに、自分だけダメなんだ。
こんな自分、もうチームに必要ないかもしれない。
セルフコンパッションを実践すると、同じ出来事をこう見つめ直せる。(「共通の人間性」の部分をオレンジで表示)
ミスをしてしまった。落ち込むのも当然だ。
でも、完璧な人間なんていない。
同じミスで悩んでいる人も、きっとどこかにいる。
同じように失敗した人たちは、どんなふうに乗り越えてきたのだろうか。
他人との比較から抜け出し「自分も人間の一人だ」と受け入れたとき、孤独感は少しずつ和らいでいく。
そして、他人もまた失敗する人間であり、その失敗を許すことが、自分への優しさにもつながっていく。
マインドフルネス(Mindfulness)
三つ目は「マインドフルネス」――今この瞬間の自分の感情や思考に、ただ気づいていることだ。
多くの人は、過去の失敗を思い返しては後悔し、未来への不安を想像しては焦ってしまう。
気づけば心は「いまここ」ではない場所をさまよっている。
マインドフルネスは、それらの感情を否定せず「ああ、今わたしは不安なんだ」「焦っているんだな」と、ただ静かに見つめる態度のことだ。
たとえば、大切なプレゼンの前に緊張しているとき。
緊張している。汗も止まらない。胃が痛い。失敗したらどうしよう。
頭が真っ白になったら恥をかく。自分はやっぱりダメだ。
もう逃げ出したい。どうして自分だけこんなに弱いんだ。
マインドフルな視点を持つと、同じ緊張がこう変わる。(「気づき」の部分をオレンジで表示)
今、心臓がドキドキしている。心は何を恐れているんだろう。
手のひらが少し汗ばんでいる。体が「頑張る準備」をしているんだ。
緊張している自分を、無理に変えようとしなくていい。ただ呼吸に意識を向けよう。
この感情は、通り過ぎる雲のようなもの。やがて静かに消えていく。
マインドフルであるということは「感情を消すこと」ではなく「感情に飲み込まれず見守ること」である。
そして、自分の感情を静かに観察できるようになると、他者の感情にもより深く共感できるようになる。
感情は敵じゃないニャ。気づいてあげるだけで、心は少し軽くなるニャ。
マインドフルネスとの違い
セルフコンパッションの三つの構成要素の一つに「マインドフルネス」がある。
しかし、広く知られている「一般的に使われるマインドフルネス」とは少し異なる。
自分に優しくするマインドフルネス
一般的に知られるマインドフルネスとは「今、ここに」集中する瞑想だ。
しかし、セルフコンパッションのマインドフルネスは「自分の心をありのまま受け入れる」ことを指す。
違いを一言でいえば、マインドフルは「自分との共感」マインドフルネスは「自分の観察」である。
違いは「感情との向き合い方」
マインドフルネス
(セルフコンパッション)
感情を〈抱きしめる〉姿勢
マインドフルネス
(一般的)
感情を〈観察する〉姿勢
👉 どちらも「いま、ここ」を大切にするが、目的が異なる
いずれも、心の安定やストレス軽減など、精神的にポジティブな効果が多くの研究で報告されている。
優しいマントラ|慈愛の瞑想
セルフコンパッションには「慈愛の瞑想(メッタ・メディテーション)」という実践もある。
これも、マインドフルやマインドフルネスとは少し性質が異なる。
慈愛の瞑想
起源は仏教の瞑想法。セルフコンパッションの源流もここにある。
優しい気持ちを呼び起こす言葉(マントラ)を心の中で繰り返し、慈しみの感情を内側から広げていく。
まず自分に向けて祈りを唱え、次にその思いやりを他者へと広げていく。
マントラの言葉に決まりはないが、ここではネフ博士が紹介している代表的なフレーズを記す。
あなたが安全でありますように。穏やかな気持ちでありますように。
健やかでありますように。安心して生きていますように。
ちなみに、私にも日々唱えているマントラがある。
光の先へ。
それは「人は誰もが光の先――つまり幸福へたどり着いてほしい」という、私自身の願いと思想を込めたマントラだ。
私の源流は物語にある。『幸せに暮らしましたとさ。めでたしめでたし』ということだ。
どれほどメルヘンだと笑われても、物語も人の人生も、結末はハッピーエンドであってほしいと願っている。
もっとも、バッドエンドにも美しさはある。だから私は、少しひねくれた物語も大好きだ。
君も、自分と他者を大切にできるようなマントラを探してみるニャ。
セルフコンパッションを育てる実践法
ここまででセルフコンパッションの概要は理解できたかもしれない。
だが「どう実践すればいいのか」「具体的な方法が分からない」と感じる人も多いだろう。
実際、セルフコンパッションはカウンセリングや心理療法の現場でも活用されている。
私は専門家ではないため、最も確実なのは、専門のプログラムを受けてみることだ。
MSC Japan(Mindful Self-Compassion Japan)
MSC(マインドフル・セルフ・コンパッション)は、セルフコンパッションのスキルを体系的にトレーニングする心理教育プログラムである。
この記事では、専門的知識ではなく、誰でも日常で実践できる普遍的な方法を紹介していく。
苦しいときに「一度立ち止まる」練習
セルフコンパッションを実践するうえで、最初のステップは「立ち止まる勇気」を持つことだ。
私たちは苦しいときほど、すぐに「どうにかしなきゃ」と行動したり、感情を押し込めたりしてしまう。
しかし、セルフコンパッションでは逆だ。何もしない時間こそが、心を癒す時間になる。
うまくいかない。
早く何とかしなければ。
こんな自分はダメだ。
そんなときは、ほんの10秒でいい。静かに深呼吸をして、「今、苦しいんだな」と気づくだけでいい。
いま、私はつらい気持ちを感じている。
なにが、こんなに苦しいのだろう?
心は、どんな言葉をかけてほしいと思っている?
これから、どうしたいと感じている?
それだけで、心は少し緩む。「苦しみを否定せず、ただ共にいる」ことがセルフコンパッションの第一歩だ。
「今、何を感じているか」に気づく
立ち止まったあとは、次のステップ――「いま、自分が何を感じているか」に気づくことだ。
苦しみに気づいたあとで大切なのは、その感情と向き合うことである。
多くの人は、つらい感情を「感じないようにする」ことでやり過ごそうとする。だが、それは心の中にフタをしているのと同じだ。
セルフコンパッションのマインドフルな姿勢では、感情を排除しない。
怒りも悲しみも、不安も――「いま、ここにある」ものとして見つめる。
なんで自分ばかりこんな目に…
こんな気持ち、もう感じたくない
どうせ誰も分かってくれない
そんなときこそ、静かに深呼吸をして、自分の内側にそっと問いかける。
この感情は、何を伝えようとしているんだろう?
私は、何に傷つき、何を求めているんだろう?
この気持ちを感じてもいい、と自分に許せるだろうか?
感情は、敵ではなく「サイン」だ。見つめることで、その根っこにある願いや痛みに気づくことができる。
気づくこと――それは、感情を癒すための第一歩。感じ切ることで、やがて静けさが訪れる。
感情は悪者じゃないニャ。心が「ここにいるよ」って教えてくれてるだけニャ。
誰もが「経験すること」だと認識する
苦しみや失敗を感じているとき、人は「自分だけがつらい」と思い込みがちだ。
しかし、セルフコンパッションでは「これは人間である以上、誰にでも起こることだ」と理解することを大切にしている。
悩み、焦り、後悔――それらは人間である証だ。
あなたが苦しむとき、世界のどこかでも誰かが同じように苦しんでいる。
自分だけが弱い
こんな気持ち、誰にもわからない
みんなうまくやっているのに、自分だけダメだ
そう感じるのは自然なことだ。けれど、その思い込みが孤独を強めてしまう。後述するが、私がそうだった。
失敗も悲しみも、みんな同じように経験している。
完璧な人間はいないし、苦しみは人生の一部なんだ。
この痛みも、きっといつか誰かを理解する力に変わる。
こうして自分の苦しみを「人間の共通体験」として捉えると、孤独感は少しずつ薄れていく。
つらさを共有すること――それこそが、人と人をつなげるやさしさの始まりである。
ひとりで泣いた夜も、誰かが同じ空の下で泣いてるニャ。だから、大丈夫ニャ。
全ての感情を抱きしめ、解き放つ
セルフコンパッションの最後のステップは、自分の感情を「抱きしめ」やがて「手放す」ことだ。
苦しみを否定せず、ただ共にいること――それが「抱きしめる」こと。
そして、十分に感じきったあと、その感情を空へと解き放つ。 それが「手放す」ことだ。
もうこの気持ちを消したい
考えないようにしなきゃ
早く立ち直らなきゃ
こうした焦りは、心をさらに縛りつけてしまう。
つらさも、怒りも、不安も、すべて〈自分〉という物語の一部。
この気持ちは、いまの私を守るために生まれたんだ。
だから、ありがとう。もう大丈夫だよ。
ネガティブな感情を抱きしめてから手放すことで、心は静かに整っていく。
それは「我慢」でも「忘却」でもない。共感と許しによる、やさしい解放だ。
セルフコンパッションの本質は、自分の中にあるあらゆる感情を愛し、やがて自由にしてあげること。
涙も怒りも、みんな生きてる証ニャ。抱きしめたぶんだけ、軽くなっていくニャ。
愛の心理学|自分と他者を愛する
セルフコンパッションの実践を続けると、やがて気づくことがある。
「自分を愛すること」と「他者を愛すること」は、同じ根から伸びている。
自分を責め続けているとき、他者のことも厳しく見てしまう。だが、自分を優しく受け入れたとき、不思議と他者にも温かくなれる。
愛の循環
- 自分を理解する → 他者の弱さにも共感できる
- 他者を受け入れる → 自分の過去も許せる
- 全てを慈しむ → 世界と調和して生きられる
これは「甘い理想」ではない。
心理学的にも、セルフコンパッションの実践は、共感力や寛容性の向上と関係していることが知られている。
この愛は誰か特別な人に向けるものではなく、自分・他者・自然・出来事すべてを包み込むような、穏やかな姿勢だ。
怒りも、悲しみも、孤独も。
喜びも、希望も、偶然の出会いも。
それらすべてを「生きている」という奇跡の一部として愛する。
自分を愛することは、他者を愛する力の始まりだ。
セルフコンパッションは世界と調和して生きるための、もっとも科学的で優しい哲学である。
「自分を愛せない人は他人を愛せない」
この言葉は、セルフコンパッションの本質をよく表している。
また、キリスト教にも次のような教えがある。
左の頬を打たれたら、右の頬も差し出しなさい。マタイによる福音書 5章39節
これは単なる「我慢」や「服従」を意味しない。報復の連鎖を断ち切る。
つまり、怒りを愛によって変える勇気を説いた言葉である。
愛とは、強さだ。自分を責めず、他者を攻撃せず、それでも歩み続ける力だ。
セルフチェック
では、ここまで学んだセルフコンパッションを、実際に自分の中で振り返ってみよう。
以下は、あなたの「自分への優しさ」や「心の向き合い方」を測るための簡単な自己チェックだ。
6項目でわかる自己チェックリスト
セルフコンパッション診断
あなたの「自分への優しさ度」を5段階でチェックしてみましょう
1=当てはまらない / 5=とても当てはまる
※この診断は自己理解を深めるための参考ツールです。
医学的・臨床的な診断ではありません。
このチェックは専門家による診断ではありません。
また、臨床現場で使われている評価表を引用しておらず、クリスティン・ネフ博士の正式なセルフコンパッション尺度(SCS)とは無関係です。
目的は「評価」ではなく、自分の心の傾向に気づくこと。その意識で進めてみてください。
また、正式なセルフコンパッション尺度を使用したい場合は、専門家監修の下記をご利用ください。
Self-Compassion Circle あなたのセルフ・コンパッションのレベルは?
結果の見方と改善のヒント
セルフコンパッションの高さ・低さは「良い」「悪い」ではなく、いまのあなたの心の状態を映すものだ。
平均が低くても落ち込む必要はない。むしろ、それに気づけたことこそが第一歩である。
スコアの目安
- 4.0〜5.0:自分を思いやる力がよく育っている。周囲にも優しさを広げられる段階。
- 3.0〜3.9:バランスの取れた状態。状況によって自己批判が出るときは「共通の人間性」を思い出そう。
- 〜2.9:自己批判が強まりやすい時期。「自分に優しい言葉」を練習してみるとよい。
改善のヒント
① 感情を否定しない ―― 「つらい」と思ったら、それを認めてあげること。
② 共通の人間性を思い出す ―― 誰もが失敗し、悩み、成長している。
③ 優しい言葉で話しかける ―― 親友にかけるような言葉を、自分自身にも。
セルフコンパッションは一瞬で変わるものではない。
だが、「気づく・受け入れる・優しくする」を少しずつ繰り返すことで、確実に育っていく。
点数よりも「今の自分を知れた」ことを大切にするニャ。
あなたの「優しさ」を育てる
セルフコンパッションは、単なる〈優しさ〉ではない。どんな形で優しさを表すかには、あなたらしい個性がある。
同じ「思いやり」でも、静かに寄り添う人もいれば、励ましの言葉で包む人もいる。
つまり、優しさにもタイプがあるのだ。
優しさの3タイプ
- 包み込むタイプ: 相手や自分の痛みに寄り添い、静かに支える。
- 励ますタイプ: 前向きな言葉で自分や他者を奮い立たせる。
- 見守るタイプ: 干渉せず、自然な成長を信じて待つ。
このどれもが「正しい優しさ」だ。大切なのは、どんなときに、どんな優しさを選ぶかに気づくこと。
たとえば、子育てにはこの3つすべての優しさが必要だろう。
- 包み込む: 我が子を思いやり、全てを受け入れる。言葉にできないときは、抱きしめて伝える。
- 励ます: 我が子が苦しんでいるとき、傍にいることを伝え、必要なときに手を差し伸べる。
- 見守る: 過剰に干渉せず、本人の成長を信じて待つ。
セルフコンパッションを育てるとは、自分の優しさの形を理解し、状況に応じて使い分ける力を養うことでもある。
包み込む優しさが欲しいときは、静かに呼吸を整えて、心を落ち着かせよう。
励ます優しさが必要なときは、自分に向かって「大丈夫」と声をかけよう。
見守る優しさが必要なときは、焦らずに、時間と流れに委ねてみよう。
優しさは、生まれ持った資質ではなく、日々の選択と経験の積み重ねによって形づくられる。
あなたの中の優しさを、少しずつ育てていけばいい。
私の経験|弱者だと思っていた自分
私自身も、セルフコンパッションを実践している。しかし、完璧とは言えない。
この章では、私の経験とセルフコンパッションの考え方を重ねて振り返ってみたい。
いじめ体験と、歪んだ認知
私は中学生のころ、いじめを受け、しばらく引きこもっていた時期がある。
その頃、私は〈物語〉に救われた。登場人物たちの強さや優しさに、自分を重ねていた。
けれど今振り返ると、あの頃の私は無意識のうちに、少し歪んだセルフコンパッションを実践していたように思う。
歪んだセルフコンパッション
「戦争で苦しんでいる人たちがいる。だから私は幸福なんだ」
「昔の人たちは生きるだけで大変だった。私は布団で眠れて、ごはんも食べられる」
「これを乗り越えたら、私の勝ちだ」
当時の私は、「自分よりも不幸な人がいる」という比較の中で、自分の苦しみを矮小化していた。
つまり、【苦しみの競争】の中にいたのだ。これは終わりのない比較ゲームだった。
それは一見ポジティブに見える。しかし実際には、自分の痛みを無視するための理屈でもあった。
「もっと不幸な人がいるから、泣いてはいけない」――それは優しさではなく、我慢だ。
セルフコンパッションとは、他者の苦しみと比較することではない。自分の苦しみをも正当に扱うことである。
それを健全な形に言い換えるなら、こうなる。
戦争で苦しむ人たちも、私も、同じように苦しんでいる。
昔の人も、今の私も、苦しみの形が違うだけ。
勝ちも負けもない。誰もが自分の人生の勝者であるべきだ。
曲がった杭
私は一時期、病的なまでに自分を否定していた。
「出る杭は打たれる。けれど、曲がった杭は捨てられる」
「いじめというのは、曲がった杭を排除する社会の自浄作用だ」
当時の私は、いじめを受けている自分を「弱者として肯定する」ことで心の均衡を保とうとしていた。
このような歪んだ自己理解は、いじめの影響だけでなく、父親から受けた暴力にも起因している。
理由は、不登校の原因として「めんどくさい」と言ったこと。いじめを知られることへの恐怖もあった。
言うまでもなく、どんな理由があろうと、いじめは決して正当化されない。人間に〈曲がった杭〉なんて存在しない。
いじめとは、身体の暴力ではなく、心理的アイデンティティの破壊である。
人間は生存のために協力し合うよう進化してきた。
他者を排除する行為は、社会の維持ではなく「共感の喪失」そのものだ。
また、いじめの加害者もまた「比較ゲーム」の中にいる。 他者を貶めることで優越感を得たいだけなのだ。
さすがに加害者にまで共感する必要はない。まずは逃げることが最優先だ。
もし今、いじめやいじりで苦しんでいるのなら、どうか助けを求めてほしい。
いじめ被害者が事実を訴えるのは、本当に難しいことだ。
経験から言えるが、いじめの告白はプライド――つまり自尊心を壊す行為のように感じてしまう。
それでも、今すぐに助けを求めよう。大丈夫。告白はあなたのプライドを壊すことではない。
それは、誇るべき勇気の証だ。
後悔の記憶から、他者への共感へ
いじめの経験は、私に「他者を想像する力」を与えてくれた。 苦しかった過去は、共感という形で生き続けている。
「暗いあの人は、どんな経験をしてきたのだろう?」
「恥ずかしがりやのあの人は、何がそうさせたのだろう?」
「人に辛く当たるあの人は、何に怯えているのだろう?」
私は人との交流が(超がつくほど)苦手だ。
それでも、この「想像する視点」は介護士としての日々を支えてくれている。
たとえば、新しい介護施設の入居者をアセスメント(情報収集と評価)するとき。
- 食事のとき、顔を上げて周りをキョロキョロしている。
👉恥ずかしがりやだろうか?(内向型の傾向?)
- 夜、明るくないと眠れない。
👉 一人だと不安なのかな? もしかすると光が「人の気配」や「安心の印」として機能しているのかもしれない。
- 周囲に誰もいないのに、突然怒り出す
👉一人でいる不安(外向型の傾向?)か、 あるいは認知症による感情のコントロール低下かもしれない。
このように、行動の裏にある〈心の理由〉を想像すると、 どんな利用者も「理解できない存在」ではなくなる。
大切なのは、ネガティブな経験や感情も、人生の一部として活かせるという自信を持つこと。
「できない」を受け入れる力
セルフコンパッションとは、「できない自分」も含めて受け入れることだ。
私は、自分のすべてをポジティブに捉えきれないでいる。しかしそれでいいと思っている。
できない私
- 基礎学力が低い(一部は中学生レベル)
- コミュニケーションが苦手(赤面を意識してしまう)
- 運動ができない(キャッチボールができない・ボウリングで10点以上取れない)
- 手先が不器用
- 音痴で、絵も描けない(どちらも壊滅的)
これらが私の人生の先行きを暗くする理由にはならない。 なぜなら、誰にだって「できないこと」はあるからだ。
そして、この「できない私」という感覚の正体は、比較ゲームだ。
もちろん、他者と比べるのをやめて努力を放棄することは、ただの逃避にすぎない。
セルフコンパッションとは、自分の限界を否定せず、前向きな失敗を重ねながら進む力のことだ。
比べるのは他者ではなく昨日の自分。 そして、その昨日の自分も、まるごと受け入れていく。
ただし「勉強を頑張ればよかった」という後悔はいまだにある
まとめ|自分の弱さごと受け入れる
- セルフコンパッションとは「失敗した自分」「弱い自分」さえも否定せず、受け入れる力である。
- それは「甘やかし」ではなく、現実を優しく受け入れる勇気であり、前に進む原動力になる。
- 3つの要素〈自分への優しさ・共通の人間性・マインドフルネス〉を意識して生きる。
- 優しさは生まれ持つ性質ではなく、毎日の選択によって育てられる。
✨ 自分を責めず、理解し、抱きしめよう。
- 弱さは、恥ではない。人間らしさの証だ。
- 優しさは、自分を愛するところから始まる。
- そして、自分を愛することは、世界を少し優しくする行為でもある。
誰もが誰かを助けられる
人は、思っているよりもずっと簡単に、誰かを救うことができる。
それは大げさな行為ではなくて、日常の中に紛れている「小さな優しさ」だ。
- 落とした財布を拾って届ける → 財布の中には、その人にとってかけがえのない思い出(写真や手紙)が入っているかもしれない。
- 道に迷っている人に声をかける → その一言が、その人の一日を明るく照らすかもしれない。
- SNSでの何気ない言葉が、見えない誰かの心を救っていることだってある。
優しさは、必ずしも目に見える形で返ってくるわけではない。 けれど、誰かの心の奥に静かに届く。
そしてその人がまた別の誰かを救う。
そうして優しさは連鎖し、見えないところで世界を少しずつ変えていく。
まるで幸せのスパイラルのように。
忘れてはいけないのは、あなた自身もまた、誰かを救える存在であり、救われる側でもあるということだ。
それは、思っている以上に小さなことから始められる。
私は、買い物のレジで「どうも」と笑顔を向ける。
飲食店では「ごちそうさまです。おいしかったです」と言うようにしている。
注目を浴びるので赤面はする。恥ずかしくて言えないこともある。
セルフコンパッションとは、自分を愛することを通して、他者への優しさを再び信じられるようになる力でもある。
免責事項
私は心理学や医療の専門家ではなく、診断や助言を行う立場にはありません。
本記事は研究や書籍、筆者の経験をもとにした参考情報です。
内容を鵜呑みにせず、必ずご自身の状況や体調と照らし合わせてお読みください。
もし違和感や不安がある場合は、公認心理師や臨床心理士などの専門家への相談もご検討ください。
具体的な相談先については、ページ下部の相談窓口にも詳しくまとめています。
参考文献
 クロ
クロ







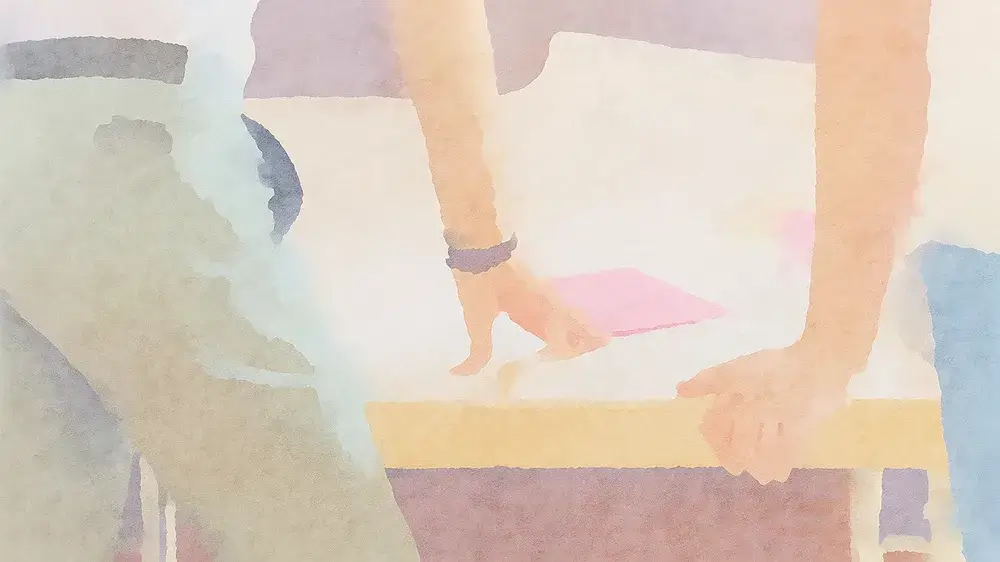
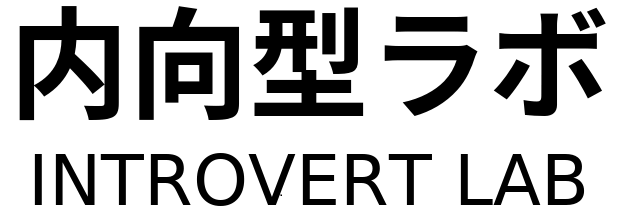



コメント